どうもマサシです。
本記事では他家のテンパイを察知するポイントについて解説します!
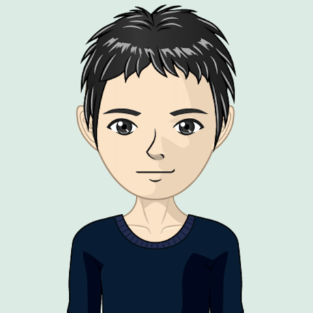
100%テンパイを察知するのはトッププロでも不可能です!ただ、テンパイを疑うべきポイントを知っておくことである程度なら察知可能です!
目次
テンパイ察知について
テンパイ宣言であるリーチを受けると降りることができるけど、ダマテンや仕掛けが入っている場合、テンパイが察知できずに放銃してしまうことがよくあります。
他家のテンパイについては当然トッププロであっても100%見抜くことはできません。
ただ麻雀上級者は察知力が高く放銃が少ないというのも事実です。
本記事では麻雀上級者が普段「あ、この人テンパイしてる」と感じる読みポイントを挙げると共に具体的な例も合わせて解説します。
テンパイを察知するポイント
まず始めに、他家のテンパイを察知するポイントを3つ挙げます。
最低限上記ポイントで挙げた事を行った人のテンパイを疑うべきです。
なぜテンパイを疑うべきなのか順に解説していきます。
副露が多い中、安全牌が手出しされた時
特に2副露以上など手牌が短い場合、なるべく手の中に安全牌を残すのは定石です。
理由は単純に手牌が短い所にリーチが飛んできたら降りにくくなるため、リスクが少なくなるようになるべく手をスリムにしておく必要があるからです。

この場合仮に⑤や5を持ってきても手に入れておかず先に切り、安全牌の北を残すのが一般的です。
逆を言うと、この「北」が手から出てきた時がテンパイサインになると言えます。
この例だと安い手ですが、高い手でも中張牌が多くごつごつしているような手牌の場合スリムにすることが多いです。
また安全牌が複数枚ある場合、危険な方から切っていくのも定石です。
例えば2枚切れの北と3枚切れの西があった場合、手が一歩進んだら北を切って西を手牌に残します。
なので3枚切れの北などより安全な牌が手から出てきた時はそれ以上安全牌を持っていないことになります。(完全な安全牌が複数枚ある場合は除き)
仕掛けてスリムな手牌にしている中で安全牌が無い=テンパイしている可能性が高いといえます。
もちろん例外もあります。
このような場合は孤立の完全安全牌をもたずに進められています。
なので
と覚えておいてください。
他家のリーチに対して無筋の牌が切られた時
他家のリーチに対して安全牌を切らず無筋の牌を切るということは、リーチに対して押しているサインとなります。
そういった場合、手の中はテンパイまたは1シャンテンであることがほとんどです。
特に親のリーチに対して無筋を押している時はほぼ確実にテンパイor高打点の1シャンテンです。
他家から高い仕掛けやリーチが来てもその人だけを見るのではなく、周りの動向をしっかり確認しましょう。
門前で押している人がいたら、リーチ者の現物で待っている(現バリ)ことも多いので合わせて注意してください。
なぜなら、「門前で押しているのにリーチしない=リーチ者の現物待ちなど和了りやすい待ち」になっている可能性が高くなるからです。
終盤、無筋や誰にも通っていない牌が切られた時
15順目などツモ番が残り少ない終盤で安全牌以外の牌が切られたらその人はテンパイしている可能性が高いです。
終盤になるとテンパイかノーテン(降り)かが鮮明に別れます。
捨て牌の数が多く安全牌に困らないため、降りるのであれば最後の数順は他家の現物など安全牌しか切られません。
一方テンパイしている場合は和了りやテンパイ料のため多少のリスクを取ります。
ド無筋までは切らないが比較的安全そうな無筋(ワンチャンスなど)や共通で通っている牌の筋牌、1枚切れの字牌くらいなら切ろう、となるのです。
もちろん最後ギリギリまで粘る人もいるので、終盤無筋を切っている人が全員テンパイとは言えませんが、テンパイの可能性はかなり高いです。
まとめ
本記事では他家のテンパイを見抜くポイントについて解説しました。
終盤戦の守備力や駆け引きは麻雀上級者と初心者〜中級者で差がつく所です。
是非参考にしてみてください!



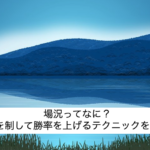
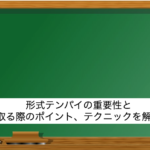

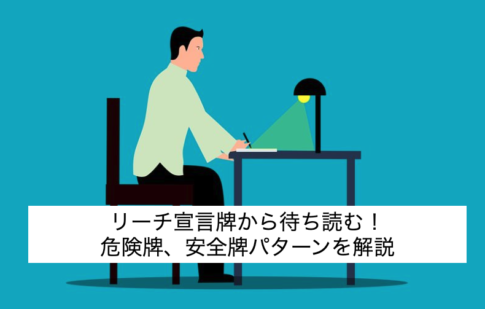
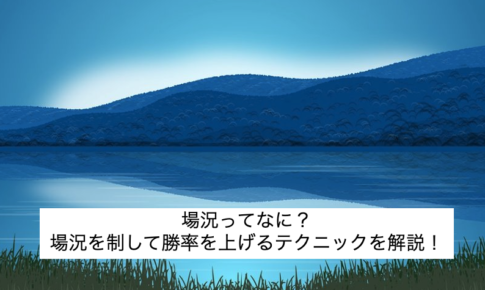

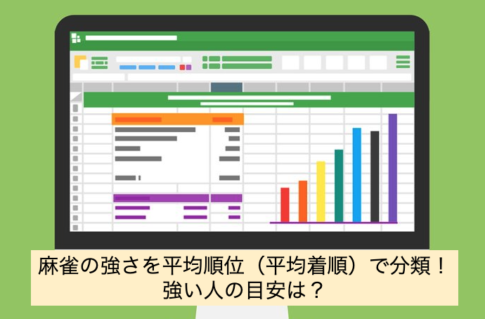
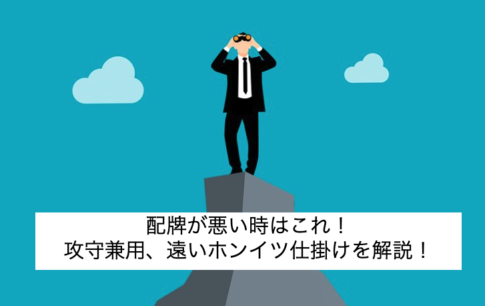
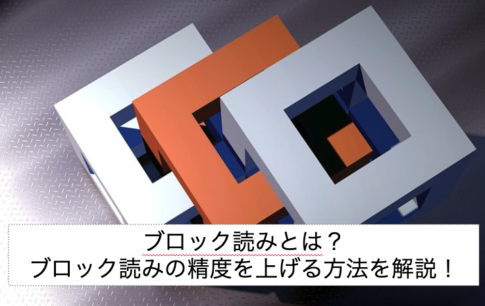

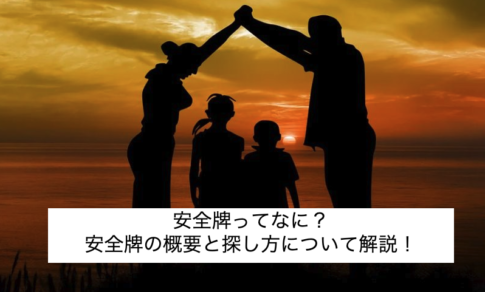
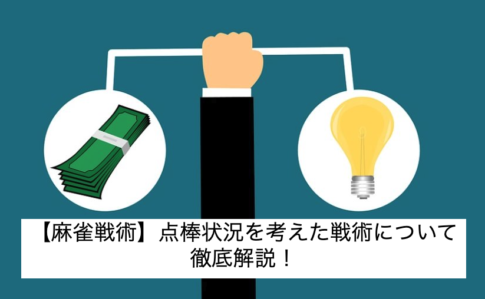
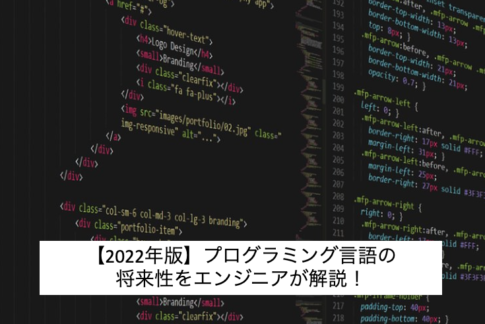

仕掛けが入っている人のテンパイはダマテンに全く気づけません。どうやったら気づけますか?